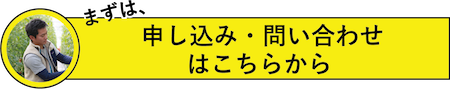新郷土料理へようこそ-紀北町魅力・ときめき第一次産業体験ツアー-
9月22日(土)から24日(月祝)にかけての三連休は、紀伊半島で新郷土料理に出会いませんか?

今回は、三重県紀北町のキーパーソンを訪ねる「紀北町魅力・ときめき第一次産業体験ツアー」に参加する人を募集します。
第一次産業とは、農業・林業・漁業のこと。このツアーで訪ねるのは「トマト農家、野菜農家、マダイ・ハタマス養殖、椎茸農家、青さのり養殖」と5人の仕事現場。

(青さのりの養殖現場です)
5人は、商品を通して第一次産業を伝える「三重 紀北町 海・山こだわり市」を開催。今後の紀北町を担うキーパーソンです。
土を使わない“養液栽培”を軸に、次々と新しい栽培技術を取り入れるトマト農家の岩本さん。バイオ研究職を経て、国内外の農場を渡り歩いたのち、紀北町の適地適作を見出した露地野菜農家の石倉さん。メディアに露出する機会は少ないものの、“絶品椎茸”をつくる加藤さん。漁業、林業、農業をマルチにこなす“半農半漁半林”スタイルの西村さん。魚の養殖のほか、海上釣り堀も営む山口さん。
5人に共通するのは、「自然から食物をつくる仕事」。一つ一つの食物が食卓に並ぶまで、数ヶ月という長い時間がかけられています。その仕事を、頭ではなく体で実感する機会をつくりたい。そこで、このツアーでは生産現場を訪ねたのちに、生産者と食卓を囲みます。ツアー後は、ぜひ各々でつながってください。
今回の告知記事では、地元のシェフに、地元食材である「トマト、ニンニク、マダイ・ハタマス、椎茸、青さのり」を料理してもらうことに。

シェフの名前は、山下智久さん。2017年12月に「ビストロモンテメール」を開業しました。
今や、日本全国のまちでローカルフードの魅力が叫ばれるようになりました。そうした中にあっても紀北町は、食材の豊かなまちだと思います。僕が魚の美味しさを知ったのは、このまちでした。そして、同じく東京出身の漫画家・元町夏央先生が移住し、「南紀の台所」(試し読みできます。ぜひ)の舞台ともなった紀北町。
山下シェフには、地元ならではの記憶がありました。
「僕の親父は漁協で働いてて。子どもの頃は毎日食卓に魚が並んでいたんです。煮付けとか刺身とか焼き魚とかね。肉、食べたかったなぁ(笑)。名古屋に出てからも、ふとアジの刺身が食べたくなるんです。でもね、魚が物足りないんですよ。年に1、2回紀北町へ帰省すると、改めてうまかったんだな、って」
料理人になって気づいたことがあるとか。
「美味いのは、魚だけじゃなかったんです。青さのりも、トマトも、ニンニクも、椎茸も、一つ一つ美味しい。そんな食材を、醤油以外の味付けで提供してみたら、どうだろうって」
フランス、イタリア、スペインとヨーロッパ各国の料理をつくる山下シェフ。
「特にフランス料理には、かしこまったイメージがあるかもしれませんね。でも実は、各地の郷土料理の集まりなんですよ」
紀北町の食材とヨーロッパの調理方法が出会うと、新しい郷土料理が生まれるようでした。
山下シェフの一皿一皿からは、生産者一人一人の目に見えない工夫や挑戦、そして同じ地域で暮らし働くつながりが見えてきます。まずは記事を読んでみて。そして、2泊3日のツアーに参加しませんか。
<東紀州の玄関口・紀北町へ>

2005年、紀伊長島町と海山町が合併して三重県紀北町は誕生しました。人口は16,000人。
山と海に囲まれ、新鮮な食材の宝庫である紀北町。三重県の南西部にあたる「東紀州」の玄関口。でもあります。名古屋から特急ワイドビュー南紀に乗り、130分。JR紀伊長島駅を降りると、スーパーオークワやドラッグストア、ファミリーマートなどが建ち並ぶ。ここから車で20分。紀勢自動車道を進み、海山インターチェンジを降りて国道42号を進むと、フランス料理店「ビストロモンテメール」が見えてきた。この日は、モンテメールを会場として生産者5名を招いてのディナーが行われました。
<“山と海”という名のフランス料理店>

フランス語の「MONT ET MER」を訳すと、「山と海」。素朴なネーミングには、山下智久シェフの考え方が表れる。
「僕はイタリアンを経て、20歳で名古屋のフランス料理店に勤めたんです。入りたての頃は、正直カッコつけた気持ちもありましたねぇ(笑)。でも料理経験を重ねるにつれて、郷土料理の集まりという、フランス料理のかざらない素顔が見えてきて」
現在38歳の山下シェフは、料理の道に入り20年を迎える。その始まりは、思い切りのよいものだった。
「『働かせてください』。高3の時、テレビ番組で見た岐阜のイタリア料理店に電話をかけたんです。同級生の中で一番早く進路を決まりましたね」
山下シェフは、2017年に実家へUターン。地元三重での独立を目指して、物件を探し始めた。県内各地で物件を探したのち、腰を据えたのは、実家から車で5分の元喫茶店だった。
<加藤椎茸店へ仕入れに向かう>
この日のディナーは19時から。時計はすでに17時を回っていたけれど、食材仕入れに向かう。山下シェフが運転する車は、5分ほどで加藤椎茸店さんへ到着。

迎えてくれたのは同級生の加藤公彦さん。椎茸栽培の決め手は、気温と湿度だという。特別に入らせてもらった培養室は、気温27度ほど。半袖では少し肌寒いくらい。椎茸の栽培方法は「原木栽培、菌床栽培、瓶栽培」と3種類あるうち、加藤さんは菌床栽培を行う。

おがくずを固めて、椎茸菌を植えつけた“ほだ木”からは、色白の椎茸たちがピンと背を伸ばしている。
「椎茸ってきれいなんですね… 」。思わずつぶやくと、加藤さん。うれしそうな表情で話し始めてくれた。
「そうなんですよ!うちは、“無農薬の1回獲り”のみを作っています」「ほだ木にはたくさんの椎茸菌が含まれています。一回獲りきったあと、しばらくすると椎茸がまた生えてくるんです」「量を求めれば、3回は収穫できるんです。でも、味が落ちてくる。紅茶とかコーヒーも2煎、3煎すると味が落ちるでしょう?同じことなんです」
<この日のコースメニュー>
今回のディナー企画は、直前に訪れた台風12号の影響もあり、バタバタと進められていった。日程が確定したのは前々日。すべての食材が決まったのは、前日。そのため、山下シェフには即興でメニューを考えていただくことに。
椎茸を片手にレストランへ戻ると、時計はすでに17時45分。ディナー開始まで、残り1時間15分。はたして間に合うのか…?
ソワソワする僕を横目に、山下シェフは「さあて、何をつくりましょうねぇ」と笑顔でメニューを書き始めた。

この後、目の前で次々と料理が生まれていくことに。
<紀北の一皿目・1回獲り椎茸のアヒージョ>

まず山下シェフが手を伸ばしたのは、加藤さんの椎茸。「きれいですねぇ」とつぶやきながら、包丁で軸を切り落としていく。「僕ね、この軸を干して使います。いいダシが出るんです。パウダーにしてもおいしいし」。
フライパンにオリーブオイルを注ぎ、石倉さんのニンニクを、みじん切りと薄切りにして入れる。「こうすると、香りが引き立つんです」。厨房にニンニクの甘い香りが広がったところで、プリプリとした椎茸が入る。あっという間に、スペイン料理・アヒージョが完成した。

<紀北の二皿目・たけチとマダイ燻製のサラダ>
続けて山下シェフが冷蔵庫から取り出したのは、自家製のマダイ燻製(くんせい)。

「脂がのって美味しいマダイの腹身です。一斗缶を加工した自作の燻製器でつくったんですよ」
真空パックを開けると、スモーキーな香りが厨房に広がった。ここで「ちょっと裏の畑に行きますね」と山下シェフ。食器にはマダイ燻製に加えて、収穫したての香草野菜、岩本さんのトマトが盛り付けられていく。最後に振りかけたのが、フライドポテトならぬ“フライド椎茸”。

「加藤椎茸店さんがつくったんですよ」
“たけチ”は、市場出荷前に傘の縁が開いた規格外品の椎茸が原材料。90%が水分という椎茸。35グラムのたけチ1袋には、300グラムの生椎茸が使われていた。

煮物などに用いられる乾燥椎茸は、いいダシが出る一方で、独特の匂いがニガテな方も多いもの。“たけチ”は旨味を残しつつ、匂いを抑えたもの。試作の末、この味つけになったという。
和食の食材としてのイメージが強い椎茸だけれど、まだまだ食べ方の可能性が潜んでいるよう。海外では“shiitake mushroom”として好まれる。
<紀北の三皿目・紀州のキッシュ>

続けて、モンテメールの看板メニューである“紀州のキッシュ”。
この一品には青さのり、トマト、椎茸、マダイ燻製、ニンニク。5人の生産者の食材がふんだんに使われている。ところでキッシュとは、フランスのアルザス=ロレーヌ地方に伝わる郷土料理。「フランスには、海藻を食べる文化がなかったんですよ」と山下シェフ。
現在、国内で700tほど生産される青さのり。その90%以上は、のりの佃煮の原材料となる“塩洗いの加工用”。一方キッシュに用いたのは、“水洗いの姿売り”。収穫後に水洗いし、乾燥させたままをいただくので、青さのり本来の風味が味わえる。
紀北町矢口浦で青さのりをつくるのは、西村友一さん。27歳で紀北町へUターンし、土木の現場で働く日々。月に一度、電波の入らない山奥で深夜に仕事中、ふと我に返った。「これができるんなら、俺なんでもできるんじゃないか?」30歳で独立して、青さのりの養殖を始めた。右も左もわからないところから、現在は、2人のスタッフとともに働く。

実は、国内生産の70%を占める三重県。青さのりのイカダが、海の畑のように浮かぶ。
ここで「西村さんとこで働いていた時期があるんですよ」と山下シェフ。「2017年に紀北町へ帰りレストランの物件を探すかたわら、『働かない?』って声をかけられて(笑)」
西村さんの青さのり養殖には、ここでなければならない理由が2つあった。
1つは完全養殖。これは、胞子体の成長から青さのりの収穫までが、矢口浦に一つのサイクルがあること。

そして“半農半林半漁”というスタイル。養殖イカダに使う木の杭は、西村さん自ら山で切り出している。それだけでもすごいなと思うのに、西村さんは野菜づくりにも取り組む。農業を始めたきっかけは、「三重 紀北町 海・山こだわり市」を通した農家との出会いだった。
<紀北の四皿目・ハタマスのアクアパッツア>
会場に、5人の生産者が集いだしたのを見て、山下さんはメインディッシュの料理を始めた。

ドンとまな板の上に置かれたのは、山口剛史さんが育てたハタマス。ゆうに5Kgはあるだろう。「大きすぎて、このままではフライパンに入りませんね」「皮がヌメヌメしてる。ゼラチン質がすごいですね…!」山下シェフも驚いている。
そこへ、早めにモンテメールへ到着した山口さん。

「ハタマスは、刺身、焼魚、カマの煮付け、アラ汁。和食の食材として余すところなくおいしい、知る人ぞ知る高級魚なもんで」
山下シェフは、どう料理するのだろう?
「完熟トマトを加えて、イタリア風の煮付け“アクアパッツア”にしましょう」
「これは…うれしいな!皮がうまいからね。ゼラチン質で良質なコラーゲンがたっぷりなもんで。ハタマスね、まだマイナーやんか。シマアジともマダイとも、同じ白身やけど味も全然ちゃうし。でもすごくおいしい魚やもんでぇ、いいね」
山下シェフが手際よく下ろすと、黒い皮とは対照的にピンクがかった白身が現れた。

切れ目に香草とともに挟んだのが、紀伊ファームの石倉至さんがつくったニンニク。
ここで、素人丸出しの質問をしてみる。「(値段が全然違うけれど、)ニンニクって、中国産と味は変わるんですか?」すると、山下シェフ。「もうね、まったくの別物ですよ。石倉さんのは臭いというよりは、香りなのかなぁ」

ここで石倉さんからも。
「糖があるんですよ。僕がつくったニンニクは、黒ニンニクの加工業者さんへ納めています。熟成すると、違いがはっきり分かります。以前に海外の黒ニンニクで食べたら、甘みがまったくなかったんです」

石倉さんは、神戸大学の農学部を卒業後、化学メーカーでバイオ研究から農業に携わってきた人。その後はカリフォルニア、山梨、長野と各地で農業を学んだのち、地元である紀北町へ。台風の通り道でもある紀伊半島で、露地栽培を営む。カボチャ、ニンニク、ヤツガシラといった生産品目にもたしかな理由があった。
「農業と一口に言っても、カリフォルニアと紀北町では気候条件が全く違います。この地に合った適地適作を模索した結果なんです。自分で農業を始めて、大事だと腑に落ちたことがあります。それは根をしっかり張ること。野菜にしっかりと味が出てくるんです」「ニンニクのにおい、味わってみてください」
厨房に漂うのは、オリーブオイルで熱したことにより生まれた甘い香り。なんだか、フルーツみたい。僕はそれまで、ニンニクに対して“臭い”とか“スタミナ”といったイメージしかなかった。安全面を理由に国産ニンニクを使っていたけれど。
山下シェフは、ガーリックオイルを何度もハタマスの皮にかけ、そこへトマト、椎茸、アサリ、ハーブが加わり… なんだかフライパンの香りが次々と育っていくみたい。
ついに、ハタマスのアクアパッツアが完成です。

<みなさんで食事会>
そして、まさかの時計は19時。取材を受けながらも手際よく調理をしてくださった山下シェフ。その料理には、ご近所の生産者たちも嬉しそうな様子。食事会が始まると、たちまち皿が空になっていきます。ここでの会話がまた、興味深かった。

「火を通しても、青さのりの香りがしっかりする」「でも、12月から4月に獲れた青さのりは、もっと青々としてるよ」「ハタマスは和食だけじゃないんだな」「生椎茸の喉越しがたまらない」「でも、椎茸の1回獲りってわかりにくいよね。2回獲りとの違いをもっと伝えたい」「原木椎茸と菌床椎茸って、どちらがおいしいのか」…
生産者と料理人。プロ同士の会話に耳をそばだてます。
レストランが盛り上がるさなか、ふたたび厨房へ。最後の仕込みをする山下シェフの姿がありました。

<紀北の五皿目・トマトデザート>

「デアルケさんのトマトはね、おいしいんですよ。糖度だけじゃない、トマトらしい風味がしっかりあるんです。僕は、好きだな」
温度や水分といった“根域ストレス”を適度にかけることで、糖やアミノ酸などが増し、トマトらしい風味をつくる。それが、株式会社デアルケです。愛知から移住した岩本さんが代表を務め、現在は11人が働いています。
岩本さんはデアルケを始める以前、トマトが土の上に生えるのか、下に生えるのかも知らなかったそう。農業には、江戸時代から変わらないイメージを持っていた。就農してから農業の先端技術に驚き、圧倒されたという。

「トマトの即席コンポートをつくりましょう」。そう言って四玉を選ぶと、山下シェフは湯せんを開始。同時に、白ワインを鍋に開けると、サッと一煮立ち。湯むきしたトマトを、香草入りの白ワインに漬けこんだ。
それだけでも美味しそうなのに。
続けて冷蔵庫からペットボトル入りの液体を取り出した。

お茶?それとも…ダシ?「自家製のトマトジュースなんです」。一口いただくと、たしかにトマトの味わい。酸味と甘みに加えて、すっと鼻を抜ける香りがある。トマトのヘタを取った時の青い香り。
「これをゼリーにしましょう」

<店仕舞いをしながら>
この日、22時にはすっかり皿が空いてからも、話は続いた。会話の内容は、「ハタマスのゼラチン質の処理の仕方」から「フルーツほおずきワインの発酵方法」、はたまた「フルーツほおずきワインの資金調達に用いたクラウドファンディング」まで。あるいは椎茸狩りを企画している加藤さんが、海上釣り堀を営む山口さんと話したり。

そして、23時30分。ようやく店仕舞いとなった。ワイングラスを拭く山下シェフに今日の感想を聞いた。
「どの食材も組み合わせやすかったです。椎茸のアヒージョに即興で入れた青さのりが、いい味を出してくれたり。ニンニクは、どの料理にも欠かすことのできない名脇役。食材は、生産者の人となりを表していました」
この日、印象的だったのは生産者のみなさんも料理人も、このまちにはプロがいるということ。
山下シェフは、紀北町の山と海を、まるごと厨房ととらえているんだな、と思った。聞けば山下さんは『熊野灘の海中に沈めて熟成発酵したワインを味わう会』を企画したり、東紀州の郷土料理“くき漬け”をパスタに取り入れたりもしているとか。
「さっき、青さのりの西村くんが『矢口(浦)に住むとは思いもしなかった。けれど、自分の足場を決めたから見えることがあるね』と話していました。僕がここにモンテメールを開いたのも、自分の足場を…、大げさに言うと死に場所を決めたようなものかもしれません(笑)」
「僕のきっかけは、“自分の店を持つこと”だったんです。紀北町ありきじゃなかった。愛知県も候補地だったんですよ。でも紀北町へ帰ってみたら、10代では気づけなかった魅力がたくさん見えてきてね。やっぱり、帰ってきたくなるまちでありたくて。この記事がきっかけで、同級生のみんなとも何かできたらうれしいなぁ。そして、初めて紀北町を知った人にも訪れてほしい。みんな個性派だし、最初はとっつきにくいと思うのだけれど(笑)。今回のツアーは、どんな人が来ても、持ち帰るものがきっとあります」
9月22日から24日にかけて行われるツアーは、14名定員とのこと。紀北町出身の方も、第一次産業をすでに考えている人も、地方での生活を考え始めた人も。どうぞ問い合わせください。